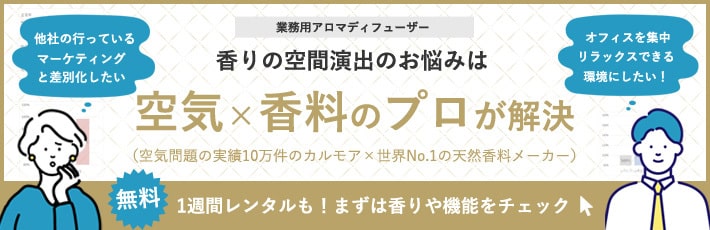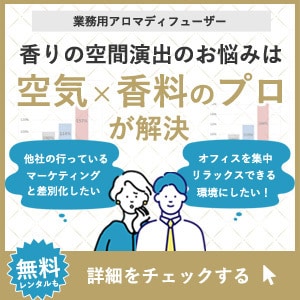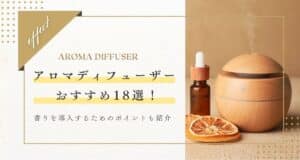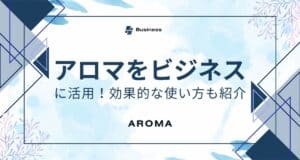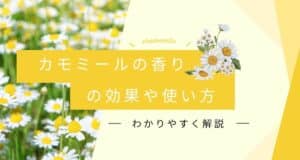「人材の確保、生産性の向上が必要だが、これ以上何をすればよいのか…」
「仕事中の緊張感をほぐすにはアロマが良いと聞いたが本当なのか?」
上記のような疑問を抱えていませんか?少子高齢化、労働人口の減少による優秀な人材確保が急務となっている昨今、新しい人材の確保と共に、今いる人材でどれだけ生産性を向上させられるか?といった点に注目が集まっています。
多くの企業が、生産性向上のために様々な試みを行っていることでしょう。例えば、人材育成を目的とした集合研修、手厚い福利厚生による人材の定着、仕事中のオン・オフを切り替えるために集中できるオフィス環境と併せて、リラックス・リフレッシュのための空間を整えるなど。
働き方改革の影響もあり、これらの中でも特に、「リラックス・リフレッシュのための空間」が大切だと考えられています。
そして、リラックスできる空間を演出する際、欠かせないのが「アロマ・香り」なのです。本記事では、そもそも「リラックス」とは、どのような状態を指すのかから、仕事中に気軽にできるリラックス方法、アロマに期待できるリラックス効果の詳細まで詳しく解説していきます。
様々な工夫を経て、全く新しい方面から生産性向上を試そうと考えているのであれば、ぜひ最後までご参考にしてください。
- 適度にリラックスできる時間を挟むことでパフォーマンスアップに
- アロマのリラックス効果は香りに含まれる芳香成分によるもの
- リラックス効果が高いアロマの一例は「ラベンダー」「ベルガモット」「ヒノキ」など
そもそもリラックスとは?仕事とリラックスの関係
リラックスとは、英語の「RELAX」からくる言葉であり、日本語でいえば「くつろぐ」「のんびりする」といった意味を持ちます。
このような意味を持つ言葉であるからこそ、従来は仕事の場面で使う必要がないとされてきました。緊張感が必要とされる仕事中に「くつろいだりのんびりしたりするなど怠慢だ」と考えられてきたのですね。
しかし、時代が進むにつれて、仕事のパフォーマンスを上げるには、ただ緊張感を重視するだけでは足りないことが分かってきたのです。ここから、仕事とリラックスの関係性・リラックスすることで得られるメリットなど見ていきましょう。
適度なリラックスでパフォーマンスを底上げできる
先述したように、昨今では仕事中も常に張り詰めた状態で業務を行うより、適度に休憩を挟むなどリラックスできる環境を整える方が仕事のパフォーマンスが上がるとされています。パフォーマンスが上がるとされる主な理由は以下の通りです。
- リラックスできる時間を設けることで、頭の中を整理できる
- 頭がすっきりすることで認知機能が高まる
- 血流が良くなることで頭・肩などの不快感が減少する
- 目を休められる
簡潔にいえば、脳・体を休めることで、低下していた認知機能や集中力を再び高められるということです。定期的に設けられた休憩時間を活用することで、ストレスコントロールも叶うでしょう。
ただ、ここで重要なポイントとなるのが「適度な休憩時間」であるという点です。休憩・リラックス時間を設けた方がパフォーマンスは上がるとされますが、だらだらと長時間休めば良いというものでもありません。実際に、数理的研究でも、仕事に伴う体力の減少・回復には一定の条件がある(※1)と示唆されています。
現在、休みなく働き続けることは論外とされていますが、パフォーマンスアップの休憩・リラックスの時間は質も必要とされることを覚えておきましょう。
過度な緊張状態が招く仕事へのデメリット
では、一昔前までは当たり前であった「休みなく働き続けることで起きうる、過度な緊張状態」が仕事に与えるデメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。主なデメリットは以下のようなものが挙げられます。
- 脳疲労により集中力・処理能力が下がる
- 特定の仕事に集中してしまい、他の業務に支障が出る
- 仕事以外の時間も仕事のことが気になってしまう
- 肩、首こりや頭痛など体調不良の遠因にも
単純に、頭や体の疲れがたまることで処理能力が下がるとされています。実際に、慢性疲労症候群患者と、健常者の「単純連続計算」を用いた実験では、計算速度において慢性疲労症候群患者の顕著な遅延が確認されました(※2)。
上記は、病を押して実験に協力されていた方たちの結果になるため、仕事による疲労と単純には比較できないかもしれません。しかし、元気な人と疲労している人を比べた際、認知機能や処理能力に差が出ることは想像に難しくないといえるでしょう。
また、デスクワークなどは同じ姿勢を続けることになるため、血流が滞り肩こりや首こり、頭痛などを発症させる恐れもあります。
忙しいから、仕事は一所懸命にするものだからと、過度な緊張状態を招くような働き方では、業務の効率・生産性を真に上げることはできないと考えられるのです。
仕事中にリラックスできる方法
上記までで、仕事中でもリラックスできる時間を設けることが大切だと分かっていただけたことと感じます。では、実際、仕事中にリラックスをするには、どのような方法があるのでしょうか?
社員がすぐにできる簡単なリラックス方法から、企業が整えるべき方法まで紹介していきます。
座りっぱなしを避ける
デスクワークなどで心がけてほしい点が、座りっぱなしを避けることです。単純に座りっぱなしなど、長時間動かないままでいると体に負担がかかるからです。
肩・首・背中・腰に負担がかかるだけではなく、目の疲れやひざ下のうっ血など、基本的に良いことはありません。
意識的に体を動かすことで、血流の改善が期待できるため、体への負担を軽減できるでしょう。また、トイレに行く、飲み物を取りに行くなど、少し机を離れるだけでも良い気分転換になります。
もちろん、集中して仕事ができること自体はとても良いことです。ただ、仕事の忙しさにかまけて体を労わることを忘れないよう意識することが大切だといえます。
なお、実際に席を立つことが難しい場合は、椅子に座ったまま背伸びをしたり軽く肩を回したりするだけでもOKです。長時間同じ体勢にならないことを心がけましょう。
意識して糖分・水分をとる
意識して糖分や水分をとる方法も有効です。
糖分は脳や体の栄養分になるだけではなく、脳神経への働きかけによってリラックス効果も期待できるとされます。甘味料によるストレスの改善効果を研究した論文では、特に砂糖のみが非常に高いストレス改善効果が見られた(※3)と発表しています。
少し疲れたと感じたときなど、自分へのご褒美として糖分をとってみましょう。特におすすめなのはチョコレート。チョコレート自体にもリラックス効果が期待できる成分が含まれているので、相乗効果が期待できるかもしれません。
また、糖分だけではなく水分も意識して摂取するようにしてみましょう。水分を摂取するには席を立つ必要も出てくるため、座りっぱなしを避けるためにも有用です。なお、リラックス効果を期待するのであれば、カフェインが含まれていない飲み物を選ぶこともポイント。
コーヒーや紅茶、エナジードリンクではなく、ハーブティーや味のついていない炭酸水などがおすすめです。
休憩室をリラックスできる環境に整える
社員が効率的にリラックスできるようにするには、企業側が環境を整えることも大切です。すぐに実践しやすい方法としては、まず休憩室の環境改善が挙げられます。
単純に「休憩室を用意して完了」ではなく、実際に利用しやすいか、リラックスできる環境になっているかを定期的に調べることも大切です。では、リラックスしやすい休憩室とはどのようなものを指すのでしょうか?
一例としては以下のようなものが挙げられます。
・オフィス、仕事場が見えない場所にある
・大き目の窓があるなど景色が見える場所に休憩室を作る
・観葉植物、フェイクグリーンなど緑の物を置く
・リラックスしやすい椅子やソファを設置する
・簡単な飲み物や食べ物を用意する
オフィスが見えない、大き目の窓が必要だとされる根拠は、休憩している際にきちんと仕事から離れられる環境であることが大切なためです。
同僚が仕事を頑張っている様を横目に、堂々と休める人はなかなかいませんよね。また、途中で止めている仕事が目に入れば、休憩中なのに仕事のことを考えてしまうことに。これでは、リラックスできる状態とはいえないため、オフィスから離れ、職場以外のものを目にできる環境が大切になるのです。
観葉植物やフェイクグリーンも、仕事に関係のないものを視界に入れることで、効率的なリラックスが期待できるアイテムです。他にも、植物の「緑色」はリラックス効果が高いことでも知られています。「緑視率」と呼ばれる、視界に入る緑色の割合によってリラックス効果が変わるため、目に留まりやすい場所に設置すると良いでしょう。
ソファや飲み物、軽食などはシンプルに休憩室に欲しいものですね。なお、これらを設置する際には、事前に社員の希望も聞いておきましょう。何事においても、上から与えるだけでは本当の意味で社員のためになっているかは図れません。
h3:リラックス効果が期待できるアロマを用いる
オフィスや休憩室の香りにこだわる方法もおすすめです。
アロマ・香りには実際的なリラックス効果があると様々な研究・論文でも認められているため、安心して導入できるはずです。
また、アロマや香りの導入は、初期費用がそこまで高額にならない点も魅力的だといえるでしょう。マイコン付きのアロマディフューザーなど、拡散方法にこだわれば、一度設置するだけで営業日のみに香りを拡散させるなどのコントロールも可能なため、社員の雑事を増やすこともありません。
ただ、アロマや香りにリラックス効果があると言われても、すぐに納得できない方も多いはずです。以下からは、アロマにリラックス効果が期待できる理由にも触れていくので、ぜひご参考にしてください。
アロマ・香りでリラックスできるメカニズム
では、なぜアロマや香りを摂取するだけで、リラックス効果が期待できるとされるのでしょうか?
リラックス効果があるとされるアロマ・香りではラベンダーが有名ですが、人によってはスピリチュアルなものだと認識されている方も多いでしょう。しかし、先述したように、アロマや香りに実際的な効果・効能があることは様々な研究・論文でも触れられています。
ここから、詳しく見ていきましょう。
アロマに含まれる芳香成分によってリラックスできる
アロマ・香りに期待できる様々な効果・効能は、アロマに含まれる「芳香成分」の生理的作用によるものと考えられています。
例えば、リラックス効果が期待できるとされるラベンダーには、自律神経に作用するような成分が含まれているということですね。自律神経の副交感神経を有意にすることで、リラックス効果が得られると考えられています。
分かりやすく例えれば、リラックスのためにアロマを選ぶというのは、健康のために食品やサプリメントを選ぶことと同じです。
「眼精疲労がひどいから目に良いブルーベリーを食べよう」「お酒を飲みすぎたからタウリンを摂ろう」など、昨今ではサプリメントや食事で栄養面を考えることは一般的ですよね。アロマも、これらサプリメントを選ぶことと同じく、摂取したい成分に着目することで、必要なアロマを選択できるようになるのです。
リラックス効果が期待できる主な芳香成分
では、リラックス効果が期待できる主な芳香成分とは、どのようなものが挙げられるのでしょうか。以下から、代表的な香りと、含まれる芳香成分・特徴を見てみましょう。
| 成分名 | 特徴 | 代表的なアロマ |
|---|---|---|
| リナロール | フローラル調の香りを持ち、不安感を和らげる効果を持つとされる | ラベンダー イランイラン ベルガモット スイートオレンジ |
| 酢酸リナリル | リナロールに酢酸が付き、エステル類になることで酢酸リナリルになる。リナロールより柔らかなフローラル調の香りやフルーティさを持ち、リラックス効果が高いとされる | ラベンダー ベルガモット プチグレン |
| リモネン | 柑橘類の多くに含まれるシトラス調の香りを持つ芳香成分。神経が正常に働くように促す効果があるとされ、この作用からリラックス効果があるとされる | レモン オレンジ グレープフルーツ ゆず |
| シトラール | レモンのように爽やかなシトラス調の香りを持つ。不安や緊張を和らげる効果があるとされる | レモン レモングラス メリッサ レモンバーベナ |
| α‐ピネン | ヒノキや杉などの木材を思わせるウッディ調の香りを持つ。抗不安・ストレス緩和作用によるリラックス効果が高いとされる | ヒノキ サイプレス ユーカリ |
「リラックスといえばラベンダー」というイメージが先行していますが、芳香成分に着目すれば、様々なアロマの選択が可能です。
オフィスの雰囲気に合わせる。または、万人受けしやすいアロマを選ぶことができるでしょう。
リラックス効果が期待できるアロマの種類は?
芳香成分別でアロマの種類に軽く触れてきましたが、全ての香りに見当が付く方ばかりではないでしょう。
ここでは、リラックス効果が期待できるアロマの香りの特徴や、おすすめ活用シーンについて触れていきます。
ラベンダー
ラベンダーは、リラックス効果があるアロマの代表格といえます。アロマや香りにさほど興味を持っていない方でも「ラベンダーといえばリラックスできる香り」というイメージを持っている方が多いでしょう。
フローラルな香りと併せて、ハーブらしいどこか青さを覚える特徴的な香りをしています。このことから、アロマの代表格でありながら、好き嫌いが分かれやすい香りでもあります。導入を考えているのであれば、事前に香りの確認をすることが必須といえるでしょう。
また、リラックス効果はもちろん、派生効果として安眠効果も期待できるとされます。そのためおすすめの活用シーンは仮眠室や、飲食物を置かない休憩スペースになります。
ベルガモット
シトラス系特有の爽やかさだけではなく、甘いフローラル調の香りを楽しめるベルガモットの香り。こちらにもリラックス効果があるとされます。含まれている芳香成分が「リモネン」「リナロール」「酢酸リナリル」と、リラックス効果が高いものばかりであるため、リラックス効果にも高い期待が持てるはずです。
少し甘めの香りを持つため、ラベンダーと同様に飲食物を置かない休憩室や仮眠室、エントランスでの活用がおすすめです。
グレープフルーツ
みずみずしく爽やかさを覚える甘さの中に、一つまみのほろ苦さを感じさせるグレープフルーツの香り。芳香成分にリモネンを含み、リラックス効果と併せてリフレッシュ効果もあるとされます。何となく憂鬱に感じる、元気が出ないと感じるときにおすすめの香りです。
爽やかで万人受けしやすく、基本的に料理の香りとケンカをしにくいため、飲食物可の休憩室でも使いやすい香り。一般的な休憩室はもちろん、オフィスでの活用もおすすめです。
レモン
香りだけで酸っぱさを覚えるような、爽やかなシトラス系特有の香りを楽しめるのがレモンです。ただ、アロマや精油になった場合のレモンの香りは、果物のレモンより柔らかに香ります。果物のレモンの香りが好きな方にとっては、少し物足りなく感じるかもしれませんね。
香りの効果は、グレープフルーツと同じく、リラックス効果と併せてフレッシュ効果も期待できます。
鮮烈さが薄いからこそ、万人受けしやすい香りになるため、アロマを置く場所を基本的に選びません。休憩室への設置はもちろん、仮眠室、エントランス、会議室など、お好みの場所で活用できるでしょう。
オレンジ
甘酸っぱいオレンジの果肉を想起させ、香りだけでもジューシーさを楽しめるオレンジの香り。ただ、一言でオレンジといっても「スイート」「ビター」の2種類があり、両者に期待できる香りの効果はほぼ同じですが、香りの印象が大きく異なります。
スイートオレンジは一般的にオレンジと聞いて思い浮かべる香りそのものです。一方ビターオレンジは、一般的なオレンジの香りに苦味を含んだ少し大人の香りになります。
スイートオレンジは休憩室やエントランス・オフィスなどで、適度なリラックス効果を実感しやすくなるでしょう。ビターオレンジは仮眠室や会議室におすすめです。
ベチバー
花や葉から香りを抽出する多くのアロマと異なり、ベチバーの香りは根から抽出します。香りの傾向も「根から採れるアロマ」のイメージ通り、少し湿った土を連想させる香りの中に、スモーキーさやカラメルのような甘さと苦さが混ざった特有の香りをしています。
「静寂の精油」とも呼ばれ、高い鎮静効果を持つとされるため、不安や緊張によって不安定になった心をリラックスさせてくれるでしょう。
雨が降る森の中のような、深い静寂を感じさせる香りになるため、雑談を楽しむ休憩室への設置より仮眠室や会議室など、落ち着きが必要な場所におすすめのアロマです。
ヒノキ
木の多い公園や新築の住宅、またはホームセンターの木材販売所などで感じる、いわゆる木の香りを楽しめるのがヒノキです。山が多い国に住む日本人にとっては、ごく身近な香りであるため、安心感を覚える面から見ても高いリラックス効果が期待できます。
含まれている芳香成分であるα-ピネンには、抗不安・ストレス緩和効果が期待できるため、職場での活用にもピッタリだといえるでしょう。
おすすめの活用シーンも多岐に渡り、一般的な休憩室はもちろん仮眠室や会議室、エントランスなど会社全体で利用できるはずです。
サイプレス
西洋ヒノキとも呼ばれるサイプレスの香りは、サイプレスの葉や球果から抽出されます。そのため、ヒノキのような木材の香りに合わせて、針葉樹の葉が持つ特有の青さを覚える香りとなっています。
ヒノキの香りが温かな印象を与えるとすれば、サイプレスは少しクールな印象を与える香りといえるでしょうか。とはいえ、ヒノキと同じく、様々な場面で使いやすいアロマといえます。おすすめの活用シーンはオフィス、会議室やエントランスなど。
ただし、サイプレスに含まれる「セドロール」は、安眠効果が高いことでも知られます。女子大学生の協力を得た実験では、覚醒状態から睡眠状態までの短縮・睡眠時間の延長傾向が見られた(※4)と発表されています。寝すぎてしまう恐れがあるため、仮眠室での利用は避けた方が良いでしょう。
職場にアロマ・香りを取り入れる方法
ここまで、職場でリラックス効果を手軽に得るために、アロマがおすすめだと解説してきました。
芳香成分やおすすめとなるアロマの種類にも触れてきましたが、いざ導入しようとしたときに気になるのが「アロマをどのように使えば良いのか?」といった点ではないでしょうか。
ここからは、職場にアロマ・香りを取り入れるための具体的な方法について解説していきます。
個人のデスク周りでアロマを焚く
オフィス全体でアロマを焚くことが難しい場合、アロマディフューザーの種類にこだわることで、ごく狭い範囲内だけでアロマを焚くことが可能です。
社員間で香りの好みが大きく異なったり、実際にアロマの効果を検証してみたりする場合におすすめです。個人のデスク周りだけにアロマを焚きたい場合は、以下のようなアロマディフューザーが便利だといえます。
| アロマディフューザーの種類 | 特徴 |
|---|---|
| アロマストーン | 陶器や石膏でできたアロマストーンと呼ばれるものに、アロマを1~2滴落として利用するアイテム。 蓋つきのケース内にアロマストーンを入れたタイプであれば、蓋をするだけで香りを閉じ込めることも可能。 |
| ティッシュ・付箋を使う | 折りたたんだティッシュや、付箋にアロマを1滴落として利用する方法。 特別に購入するものがないため、すぐに試せる。また、オイルが揮発するスピードが速いため、短時間だけ試したい場合にもおすすめ。 |
| USB式アロマディフューザー | パソコンのUSBポートなどから充電できるアロマディフューザー。 手のひらサイズのコンパクトなものが多いため、香りの拡散力も弱め。機種によって拡散力が異なるため、実際に利用する前に試運転をしておきましょう。 |
特におすすめになるのは、アロマストーンの利用です。ストーン自体のデザイン性が高かったり、ストーンを入れる容器がお洒落だったりするので、視覚の面からも楽しめるでしょう。
アロマペンダントを活用する
アロマペンダントとは、文字通りペンダントトップの部分にアロマオイルを入れたり、しみこませたりして身に付けられるアイテムを指します。香りを拡散させるというより、香水をまとうように利用できるため、個人でアロマを楽しみたいときに便利なアイテムといえるでしょう。
製品によって香りの持続時間は異なりますが、香りが広がる範囲は付けている人を中心に1m程度です。
ただ、使用するアロマオイルの量によっては、周りへの拡散力が強くなりすぎることもあります。職場で使うのなら、ごく少量から使ったり、説明書に書かれている容量を守ったりすることもポイントです。
アロマディフューザーで香り空間を演出する
休憩室やオフィス全体にアロマを拡散させたいのなら、アロマディフューザーを用いる方法がおすすめです。アロマディフューザーは、もともと空間に香りを拡散させるアイテムなので、効率よくアロマの香りを拡散してくれます。
なお、オフィスや休憩所など、個人宅の一室より拡散させたい空間が広い場合は、一般的なアロマディフューザーではなく業務用アロマディフューザーを利用しましょう。
単純に、一般的なアロマディフューザーでは、拡散能力が低く香りを隅々まで届けられないためです。特に、天井が高い空間に用いる場合は、市販のアロマディフューザーでは力不足なことがほとんどです。
一方、業務用アロマディフューザーであれば、拡散力が強いだけではなく、壁掛けタイプやダクト直結型など市販されているアロマディフューザーとは異なる取り付け方も選択できます。
アロマを導入する空間の広さや、人の出入りの多寡も加味しながらアロマディフューザーを選んでください。
職場にアロマを取り入れる際の注意点
ここまでアロマに期待できる効果や、具体的な使い方について解説してきました。
実際的な効果が期待できるとなれば、アロマの導入を前向きに考えたくなった方もおられるでしょう。しかし、アロマには実際的な効果が期待できるからこそ、知っておかなければならない注意点もあります。
導入後に「そんなことは知らなかった」とならないよう、事前に考えられるデメリットや注意点も確認しておきましょう。
アロマ・香りを選ぶ際には個人の好みだけで選ばない
一番に知っておくべき注意点は、アロマ・香りを選ぶ際に個人の好みだけで選ばないという点です。なぜなら、アロマに限らず、ニオイというものは人によって好き嫌いが大きく分かれるからです。
特定の人にとって良い香りであったとしても、他の誰かにとっては集中力が乱される香りである可能性があります。そして、同じ人・同じ香りであっても、その日の体調や天気(温度・湿度)によって、香りに感じる印象が異なることもあるのです。
観葉植物や絵画のようなものであれば、見たくなければ目を瞑ったり背けたりすることができますよね。しかし、嗅覚は嗅ぎたくないと思っても、鼻の穴を閉じることは難しいもの。苦手なにおいに常時囲まれるようになれば、リラックスどころか最悪退職の原因にもなりかねません。
このような事態を招かないためにも、アロマ・香りを選ぶ際には個人の好みだけで選ばないことが大切なのです。事前にサンプルを用意して、社員たちに香りを選んでもらえば、最大公約数的なアロマを選ぶことができるはずです。
アロマによってはアレルギー反応が出る可能性があることを知っておく
続いての知っておくべき注意点は、アロマの種類や人によってはアレルギー反応が出る可能性があることです。
アレルギー反応が出やすいのは、多くの場合、精油をスキンケアなどに使った場合です。しかし、香りに含まれる成分に反応しないとは言い切れません。
特に低品質なアロマを用いた場合は、芳香成分ではなく香りを作っている石油や化学製品へのアレルギーを起こしている可能性も考えられます。多人数がいる場所でアロマを用いるのであれば、事前の確認と併せて、アロマ自体の品質にも気を配りましょう。
香り空間の演出時はアロマの濃度にも気を配る
実際に社員に好評なアロマを選べた後は、アロマディフューザーなどを用いて香りを拡散させることになります。このときに気を付けるべきポイントとして、香りの種類だけではなく濃度にも気を配る必要があることを知っておきましょう。
どれだけ良い香りであっても、濃度が高すぎると不快に感じがちです。どの程度の濃度の香りを心地良いと感じるかも人によるため、初めは低めの濃度から試していくと良いでしょう。
もう一つのポイントとして、同じ香りを長時間使っていると、嗅覚が慣れて香りを感じにくくなることがあります。香りに慣れて感じにくくなっているだけなのに「アロマオイルが少なくなっているのか?」「ディフューザーが弱いのか?」と、濃度を上げてしまうことがあります。
この状態が続くと、はじめはほのかに香る程度だったアロマが、いつの間にか濃くなっていたという事態になりがちです。慣れていない人にとっては気分が悪くなってしまう可能性もあるため、本格的にアロマを導入した後は、むやみに拡散力を変更しないよう気を付けましょう。
当社取扱製品「シュヴァリテエール」の導入事例を紹介
アロマのリラックス効果や取り入れ方を解説してきました。ただ、机上でアロマにはリラックス効果があるといわれても、実際の例を見なければ納得できないという方もおられるでしょう。
そこで、ここからは、当社が扱う「シュヴァリテエール」を導入し、リラックス効果・癒し空間が実現できたとお声をいただいた事例について紹介します。
高齢者向け内科クリニックへの導入事例
高齢者向け内科だけではなく、精神科も扱われているクリニックへの導入事例です。患者様自身が感じる健康への不安や戸惑いはもちろん、付き添われるご家族様もリラックスして診察を受けられるようにとご希望をいただきました。
香り演出を指定された待合室は、細長く奥行きがあるスペースになっていたため、当社がご提案したのは拡散力が高い中・大規模スペース用の「SA-F-500」。お客様に選んでいただいた香りは「シトラスハーバル」です。
お客様自身にも良い香りだと好評価をいただいた今回の香りは、クリニックに通う患者様のご家族様からも嬉しいお手紙をいただける結果に。通院が安らげるひと時になったとのお言葉は、当社社員のやる気を高める結果にもつながったと感じています。
・アロマディフューザーの導入効果について
| ◎ご利用いただいたフレグランスは爽やかな「シトラスハーバル」 ◎奥行きがある場所でも拡散力が高い「SA-F-500」で十分な香り空間を演出 ◎お客様を始め、患者様のご家族様からも通院が癒しのひと時になったとのお言葉をいただきました |
オフィスの商談スペースを癒し空間へと変えるための導入事例
本社の移転を機に、新しく作る商談スペース兼リラックススペースへの導入事例です。社員様がリラックスできる空間演出はもちろん、商談スペースも兼ねているため「作業効率が向上するような香り」とのご要望をいただきました。
当社が扱っている香りの中で、最もリラックス効果が高いとされている香りのご提案。そして、リラックススペースではコーヒーメーカーなど、ディフューザー以外にも香りの発生源があったため、2週間のトライアル期間を使い、空気の流れを読みながら香り同士がけんかをしない設置位置を慎重に決めてまいりました。
結果的には、お客様にイメージ通りの空間演出ができたとお褒めの言葉をいただけました。リラックススペースだけではなく、エレベーターホールにもわずかに香りが流れるようにしたため、来訪したお客様からもご好評もいただけているようです。
・アロマディフューザーの導入効果について
| ◎2週間のトライアル期間で実際の香りを確認できる ◎トライアル期間を使って、アロマディフューザーの最適な設置場所を決定 ◎イメージ通りの空間演出ができたとお褒めの言葉をいただけました |
まとめ
本記事では仕事中にリラックスすることの重要性から、手軽にリラックスをする方法、アロマによってリラックスできる理由やおすすめの香りについて紹介してきました。
最後に、おすすめの香りについて軽くおさらいをしておきましょう。
・ラベンダー
・ベルガモット
・グレープフルーツ
・レモン
・オレンジ
・ベチバー
・ヒノキ
・サイプレス
どのアロマも、高いリラックス効果を持つとされるため、仕事中に感じる緊張を効率的にほぐしてくれるでしょう。心地よい香りは、リラックスできることはもちろん、職場の雰囲気を明るくしてくれる効果も期待できます。
なかなか生産性が向上しないと悩むだけではなく、社員の定着率が低いなどのお悩み解決の一助にもなってくれるでしょう。
とはいえ、注意点でも触れてきたように、アロマや香りには一定の効果があるからこそ、扱いが難しい面もあります。「なんだか難しそう」「メリット部分は魅力的だけれど、デメリットを自社だけで解決できそうにない…」このようにアロマ導入に二の足を踏まれるようであれば、ぜひお気軽に当社にご相談ください。
香りはもちろん、消臭問題に長年真摯に取り組んできた当社スタッフが、お客様が望む空間演出を全面的にサポートいたします。
参考文献・論文URL:
(※1)https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/pdf/1966-03.pdf
(※2)https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/guide/efforts/research/kuratsune/h21-23/pdf/h21-23bun02.pdf
(※3)https://cir.nii.ac.jp/crid/1390564238088619904
(※4)https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpa/8/2/8_KJ00001053451/_pdf/-char/ja
参考URL:
https://haa.athuman.com/media/psychology/relax/832/?doing_wp_cron=1745217732.2738640308380126953125